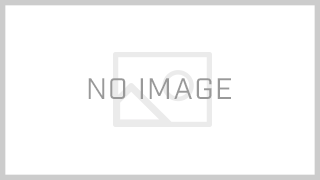体の不調には、関節痛や倦怠感、偏頭痛など、さまざまな症状があります。そのような問題が出現した場合、「関節痛であれば整形外科」というように、それぞれに適した病院を受診します。
ただ、どの病院に行っても不調が改善せずに長年悩まされる人も少なくありません。そのような場合、全身に「慢性炎症」が生じている可能性があります。
そして、慢性炎症を引き起こすきっかけに「リーキーガット」という問題があります。慢性的な体の不調に悩まされる人の多くに、このリーキーガットが関係しているといわれています。
そこで今回は、慢性的な体の不調を引き起こす「リーキーガット」について解説します。
慢性炎症と病気の関係
人の体には、皮膚を擦りむいたときや風邪にかかったときなどに、自分自身で治す「自然治癒力」と呼ばれる力が備わっています。この自然治癒力を起こすシステムのことを炎症といいます。
いわゆる炎症反応では、炎症部位に発赤や発熱、疼痛、腫脹が起こります。これは、傷ついた組織を修復するために生じる自然治癒反応といえます。
そして、炎症には急性炎症と慢性炎症があります。急性炎症は、先ほど述べたような体が治癒するために必要な反応です。明らかな腫れや強い痛みを伴うことがほとんどですが、炎症を引き起こしている原因を除去すれば、症状も落ち着きます。
一方で慢性炎症は、急性炎症のように強い症状は出現しません。しかし慢性炎症では、低レベルの問題がいつまでも持続します。
そして、このような慢性炎症は、さまざまな慢性疾患の原因になります。例えば、以下のような疾患は、慢性炎症が関係しているといわれています。
・がん
・自己免疫疾患
・糖尿病
・動脈硬化
・アルツハイマー病
・骨粗しょう症
・メタボリックシンドローム
このように、病院で原因がはっきりと指摘されない病気の多くは、体に起こった慢性炎症が関係しています。そのため、このような慢性病を予防するためには、体に慢性炎症を発生させないことが大切です。
慢性炎症を引き起こす「リーキーガット」
前述したように、慢性炎症は、さまざまな病気の原因になります。そして、慢性炎症を予防するためには、食生活に注意しなければいけません。
慢性炎症は「NF-カッパ-B」と呼ばれる物質が原因で起こります。このNF-カッパ-Bが活性化されると、体内で慢性炎症が発生することになります。
そして、NF-カッパ-B細胞を活性化させる要因には、以下のようなものがあります。
・ウイルスなどの感染
・重金属や放射性物質などの毒性物質
・食事、睡眠、ストレスなどの生活習慣
この中でも、特に注意すべきことは食事です。感染や毒性物質などは、いくら気をつけても避けることが難しいものです。一方食事であれば、あなたが気をつければ変えることができます。
通常、食べた物は腸によって「体にとって害があるものかどうか」を識別されます。そして、害がないと判断されれば血液中に吸収され全身に回ります。もし腸に入った食品が有害と認識された場合は、免疫反応によってその異物の多くは便として体外に排泄されますます。
これは、腸内に存在する腸内細菌によるバリア機能です。健康であれば、腸内細菌によってバクテリアや巨大なタンパク質といった、体にとっての異物は排除されます。
しかし、このような腸内細菌叢に異常が生じると、腸の壁が薄くなったり穴が開いたりします。その結果、腸におけるバリア機能が低下してしまうため、血液中に異物が侵入してしまいます。このような状態を「リーキーガット」といいます。
「リーク」とは漏れる、「ガット」とは腸を意味します。つまり、リーキーガットとは「腸の粘膜から物質が漏れ出る状態」のことを指します。
リーキーガットの状態では、本来であれば腸内細菌によって排除される異物が、簡単に血液中に侵入して全身に回ってしまいます。その異物が、慢性炎症の原因であるNF-カッパ-Bを活性化させます。
つまり、リーキーガットが慢性炎症の原因となり、さまざまな慢性病を引き起こすきっかけとなります。そして、リーキーガットは、食生活の乱れによって生じることが明らかになっています。
今回述べたように、慢性炎症はさまざまな慢性病の原因となります。そして腸に生じるリーキーガットは、慢性炎症を誘発する大きな要因となります。リーキーガットは食生活の乱れから生じるため、慢性病を予防するためには、普段の生活習慣に気をつけることが大切です。