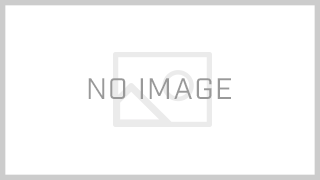筋力低下は、多くの人が悩まされている症状の一つだと思います。ひざや腰などに痛みがあるときに病院に行くと、ほとんどの場合、筋力の低下を指摘されて筋力を強くすることを指示されます。
確かに、加齢によって筋力が低下することは事実です。しかし、実際に病院に来られる方の多くは、「真の筋力低下」を起こしていません。大半の人は「見せかけの筋力低下」によって、筋力が落ちている様に見えています。
このことを理解しておかないと、健康のために行っている運動が、逆に体を壊すことになりかねません。そこで今回は、筋力について解説します。
筋力は筋肉量に依存する
通常の健康な人の場合、発揮される筋力は筋肉量に比例します。つまり、筋肉量が多ければ多いほど力が発揮されるということです。例えば、筋肉量が100あれば、発揮される力も100、筋肉量が80であれば、発揮される力も80といった具合です。
このような場合は、筋肉量が低下することで、実際に発揮される力も落ちてしまいます。これが「真の筋力低下」です。加齢による筋力の衰えやベッド上での寝たきり生活で起こる廃用性の筋力低下などがこれに当たります。
しかし、実は体に痛みを抱えている人の多くは、この「真の筋力低下」ではなく「見せかけの筋力低下」を起こしているのです。
見せかけの筋力低下とは、筋肉量に比べて発揮される力が弱くなっている状態を指します。例えば、通常では、筋肉量が100あれば、力も100発揮されます。しかし、見せかけの筋力低下がある場合、筋肉量が100あるのに、80の力しか出せないという状態になっています。
つまり、筋肉は充分あるけれども、筋肉を上手く使えていないという状態です。このような場合は、筋肉量には問題ないため、いくら筋トレを行っても筋力は上がりません。
見せかけの筋力低下はなぜ生じるのか?
人の体には、基本的な物理の法則が成り立ちます。その法則の中に、「作用反作用の法則」というものがあります。これは、ある物体Aから物体Bにある力C(作用力)が加わるとき、物体Aには反作用力としてCと同じ力が返ってくるということです。
体で説明すると、歩行時に床に対して体重分の力が加わります。その際、足から体にかけて、その体重分と同じ力の反作用力が返ってくるということです。
そして、体にはこの反作用力に対応する機能が必要になります。もし体に、反作用力を打ち消すような機能がなければ、その力で体は壊れます。つまり、「体は自身が吸収できる分の力しか発揮しない」ということです。
そのため、反作用力を吸収する体の機能に問題がある場合に、見せかけの筋力低下が起こるということです。病院で筋力低下を指摘される人の大半は、この見せかけの筋力低下です。
つまり、発揮される筋力は体の衝撃吸収機能に依存しているということです。
そして、このように見せかけの筋力低下が起こっている場合には、筋力トレーニングではなく、反作用力の吸収機能を高めることが必要になります。
衝撃吸収機能は背骨がその大半を担っている
人の体において、反作用力を受け取るものは「背骨」になります。背骨は、前後にS字状の凹凸があります。このS字状の弯曲(わんきょく)構造によって、体にかかる力を吸収します。
このS字弯曲は、進化の過程で四足歩行から二足歩行になった際に獲得されました。この構造によって、二足歩行になることで求められる「高度なバランス能力」や「上半身の体重を吸収する機能」を得ることができ、二足歩行での生活を可能にしました。
さらに、このS字状の弯曲構造は「バネ」のように作用し、体にかかる反作用力を吸収する機能を担うようになりました。背骨には、このように大事な機能が求められているのです。
つまり、病院で筋力低下を指摘される多くの人は、筋肉量に問題があるのではなく、背骨のS字構造が崩れているために、筋力が発揮できていない状態であるということです。そのため、そのような人々に必要なことは、筋トレではなく、背骨の柔軟性を改善するような運動です。
以上のように、見せかけの筋力低下は背骨のS字構造の問題から起こります。背骨に問題がある状態で筋トレをしてしまうと、体は壊れます。つまり、筋力の低下を指摘された場合は、まず背骨の問題を疑う必要があるということです。