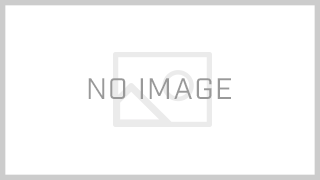血液の流れが適切であることは、体の健康にとって大切です。このことは、誰もが納得できることだと思います。血流が悪くなると、細胞に栄養があまり届かなくなります。これにより、それぞれの組織が十分に働けなくなります。特に末端には、血液が届かなくなるため、手足が冷えます。
このように、血流が円滑であることは、生命を維持する上で欠かせないものです。そのため、血流の仕組みを理解しておくことが大切です。
そこで今回は、血流の仕組みについて解説します。
動脈と静脈
血液には、主に2つの役割があります。1つは、全身の細胞に酸素や栄養、免疫細胞を届けることです。もう1つは、全身の細胞から、不要となった二酸化炭素や老廃物を回収することです。そのため、血流の流れが悪くなると、さまざまな不調が出現します。
血液を送るための器官は「血管」です。血管は、総長9万キロメートルもあり、約地球2周分の長さがあります。血液は、このような血管内を流れています。
そして、先ほど述べた血液の2つの役割によって、使われる血管の種類が異なります。
全身の細胞に酸素や栄養などを送る血管を「動脈」といいます。そして、動脈を流れる血液を「動脈血」と呼びます。そのため、動脈血には、酸素や栄養素などが豊富に含まれています。
動脈は、血管の壁が厚く、弾性が高いという特徴があります。そのような特性から、血管の収縮と弛緩を行うことで、隅々の細胞まで勢いよく動脈血を送ります。
一方、全身の細胞から二酸化炭素や老廃物を回収する血管を「静脈」といいます。そして、静脈を流れる血液を「静脈血」といいます。そのため、静脈血には、二酸化炭素や老廃物など、組織に必要のなくなったものが豊富に含まれています。
静脈は、動脈と比べると、血管の壁が薄く、弾性も低いです。これは、血液をスムーズに心臓に戻せるようにするために、薄く伸びやすくできているのです。
筋肉の衰えが高血圧につながる理由
静脈血には、自分自身で動く力はありません。一方、心臓は動脈血を押し出す力はありますが、静脈血を吸い上げる力はもっていません。そのため、上半身の静脈血は重力で、楽に心臓へ戻れますが、下半身の静脈血は重力に逆らって心臓に返る必要があります。
このときに必要になるのが、下半身の筋肉です。静脈は筋肉の中を走っています。そのため、筋肉は収縮、弛緩することによって、静脈に圧力を加えて、ポンプの役割を果たします。
このように、下半身の静脈血は、筋肉によって心臓に戻ります。つまり、筋肉が衰えると、静脈血の流れは滞るということです。そうなると、むくみなどの症状が出現します。さらに、そのような状態では、心臓に返る血液量が少なくなります。そのため、結果的に送り出すための血液量も減ります。
そうなると、少ない血液量を全身に送ろうとして、体は心臓を強く働かせ、血管の圧力を高めます。これが、高齢者の血圧が高い理由です。高齢者は、加齢による筋肉の委縮によって血液の流れが悪くなっています。そのため、高齢者の体は、血圧を上げることで、末梢まで血液を送ろうとするのです。
体循環と肺循環
また、血液の循環路は体循環と肺循環の2つに分類されます。体循環は、心臓と全身の細胞をつなぐ経路です。一方、肺循環は、心臓と肺をつなぐ血管路です。
体循環では、心臓のポンプ作用で、酸素と栄養素を含んだ血液が動脈に押し出され、全身の細胞に送られます。そして、細胞から二酸化炭素や老廃物などを回収し、静脈を通って心臓に戻ります。
肺循環では、体循環を回って、心臓に戻った静脈血が肺の動脈を通ることで、酸素を受け取ります。そして、新しく酸素を含んだ動脈血となり、心臓に返ります。その後、また心臓のポンプ機能によって全身に送られるという流れになります。
今回述べたように、動脈、静脈には、それぞれ特徴と役割があります。このことを理解しておくことで、高血圧など、血管に関するような症状に対する考え方が変わります。
そして、このような体の基本的な機能を学ぶことは、結果的に、あなたが悩まされている症状を解消するヒントになります。