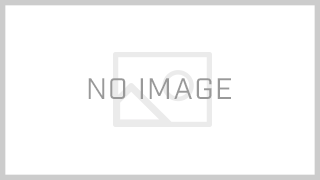体内には成人で60%、赤ちゃんで70~80%の水分が存在しています。体内の水分は、血液や組織、細胞の間を満たしている組織液、リンパ液などとなって全身をめぐっています。水分の20%が失われると死に至ると言われており、水は体温の調整、栄養分の運搬、不要物の排出といった生命維持において重要な役割を担っています。
熱中症で気分が悪くなってしまうのも、体内の水分不足がその一因です。いま一度、水分を摂取することの重要性を学んでいきましょう。
1日の水分摂取量と排出量
私たちは、食事や飲料水から水分の摂取をしています。食事からの摂取量は1,000ml、体内での代謝による水分の生成が200mlと言われています。
1日で失われる水分量はおよそ2,500mlであるため、1,500mlほどを食事以外から摂る必要があります。
普段、水を1~2杯ほどしか飲まないという方は、慢性的な水分不足に陥っているかもしれません。水分不足は集中力低下、代謝機能の低下、体温調整機能の低下など、人の生理機能に悪影響を及ぼします。
では、どのくらいの量を普段から摂取すべきでしょうか。
オススメの摂取量とタイミング
一番は「喉が乾ききる前に水を飲む」ことを意識しましょう。喉が乾ききっている状態では、すでに軽い脱水症状が起きていると言われています。これでは、代謝機能などの活動低下を招きます。このことから、こまめに水分を取ることが重要です。
仕事や活動量によっても異なりますが、デスクワークや勉強など、比較的静的な活動の場合は1~2時間おきに200ccが目安です。スポーツや汗をかくような活動がメインの場合は、15分~30分おきに200ccほどを目安に水分補給をしましょう。
人は日々の生活の中で少しずつ水分を失っていくので、「1度にたくさん」より「こまめに少しずつ」を意識して取る方がいいでしょう。
また就寝の前後は、水分を摂取すべき一番のタイミングです。睡眠は、日中活動した脳や身体を休めるだけでなく、溜まった老廃物を排出する時間でもあります。このときに水分が足りないと、老廃物がたまる要因となってしまいます。
特に「朝起きるといつも身体がだるい」「すっきり起きられない」という方は、就寝前にコップ1杯の水を摂取してから寝てみて下さい。
朝起きた時にも、コップ1杯の水を取りましょう。睡眠中は汗をたくさんかきます。その量は成人で200~400ccとも言われています。
起床時には発汗により水分が失われ、血液がドロドロとした状態になりやすくなっています。朝のコップ1杯の水は、流れにくくなった血液を流しやすくして、活動的な身体になるスイッチとして作用します。
どのような水分を摂るべきか
水分補給といっても、全てが水分補給に適しているわけではありません。例えば、ビールなどのアルコール飲料は利尿作用(尿を出しやすくする働き)があります。清涼飲料水などのジュース類も、糖分が多く含まれているため、飲み過ぎは別の疾病の原因になる可能性があります。
汗をたくさんかくことがないようであれば、「水」そのもので十分です。炎天下の運動や、一日汗をかくような仕事をする場合は、1.5~2倍に薄めたスポーツドリンクが良いでしょう。スポーツドリンクには、ナトリウムと運動に必要な糖分が含まれています。
汗をかくと、水分と一緒にナトリウムも失われていきます。ナトリウムは体内の水分量の調節に役立っており、その補給にスポーツドリンクは適しています。
ただし、スポーツドリンクには糖分も余分に含まれているので、そのまま飲んでしまうと水分の吸収が遅れてしまいます。そこで、前述のとおり水で薄めてから飲むことで、失われた水分とナトリウム、糖分を効率よく摂取できます。
普段、水分補給は意識的に行わないと忘れがちです。特に運動時や睡眠中には思った以上に水分が失われていきます。「代謝が落ちた」「疲れやすくなった」と感じる方は、ぜひいつも以上に生活の中で水を摂取してみてください。