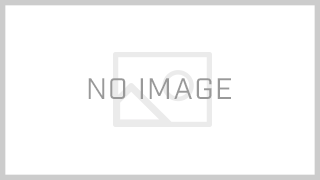あなたは「筋力トレーニングの原則」をご存知でしょうか。この原則は、「効率よく・正しく・安全に」筋力をつけていくために欠かせないものです。トレーニングは、ただやみくもにしていても効果は得られません。
トレーニングの効果が思ったより得られないときは、この原則に反していることがあります。そして、「筋肉トレーニングの原則」は8つあります。
そこで今回は、その8つについて解説します。
・過負荷の原則
筋肉は、自分が持ち上げられる限界よりも、強い負荷をかけなければ成長しないという原則です。負荷とは、トレーニングに使用する器具の重さや、運動時間によって身体にかかるストレスのことを言います。
筋肉は、トレーニングによって破壊された筋細胞組織や筋繊維が、より太くなることで成長していきます。筋力がアップして重さに慣れた段階で、徐々に負荷も強くしていきましょう。
・漸進性の原則
筋肉は筋力の向上に応じて、徐々に負荷を強くしていく必要があるという原則です。
これは、過負荷の原則と近い性質になります。
一般的に筋肉は、運動を重ねるごとに、前回の運動レベルのダメージに耐え得る筋肉へと変化していきます。そのため、少しずつトレーニングの負荷を強くしていかなければなりません。ただし、急激に負荷を強くすると怪我の原因になるので注意が必要です。
・意識性の原則
トレーニングの「目的」「効果」「方法」を頭で理解した上で実践すると、より効果が高くなるという原則です。
例えば、何も考えずに重りの上げ下げを繰り返すのではなく、具体的に鍛えている筋肉を意識したり、筋肉の収縮をイメージしてトレーニングをした方が効果的です。そのため、行っている運動がどの筋肉を使う運動なのかを学ぶことも大切です。
また、トレーニング中は、動かしている部位に集中することが大切です。実際に鏡を使うなどし、動いている筋肉の動きを見ることも有効です。
・特異性の原則
運動の効果は、実際にトレーニングをした部位にしか表れないという原則です。スクワットという動作(太ももやお尻が鍛えられる)をして、腕に筋肉がつくことはありません。
これは、意識の原則に近い性質を持ちます。スポーツをしている方は、そのスポーツの特徴にあった筋肉や、動き方をイメージしながらトレーニングするとより効果的です。
・継続性の原則
筋肉は、一定期間以上トレーニングをしなければ効果は得られないという原則です。一回のトレーニングでは効果はでません。通常、効果が現れるには1~3ヵ月ほどの期間が必要と言われています。
継続してトレーニングを行うためにも、無理のない計画を立て、モチベーションを維持することも大切です。
・可逆性の原則
筋肉は、負荷をかけ続ければ成長し、止めると衰えていくという原則です。
継続性の原則と近い性質を持ちます。その衰えるスピードは、筋肉を身につけたスピードに比例すると言われています。そのため、筋力が落ちないように少ない負荷でも筋力トレーニングを継続することが大切です。
・個別性の原則
筋力トレーニングは、その人に合った内容を考えなければいけないという原則です。
人はそれぞれ年齢、性別、体格、体質、トレーニングの目的が違うので、メニューも変わってきます。その人に合ったメニューを作成することが重要です。
・全面性の原則
全身の筋肉をバランス良く鍛える必要があるという原則です。例えば、腹筋だけ鍛えても背筋が弱いと腰痛の原因になります。さらに、かえって姿勢が悪くなり身体の負担になることもあります。
また、体力向上のためには筋力だけでなく、柔軟性や敏捷性、筋持久力といったさまざまな要素をトレーニングをすることが重要です。
この8つの原則は、意識的に行わないと忘れがちになってしまいます。普段のトレーニングはもちろん、トレーニングメニューを立てるときや、効果が出なくなってきたと感じたときにこの原則を思い出してみましょう。